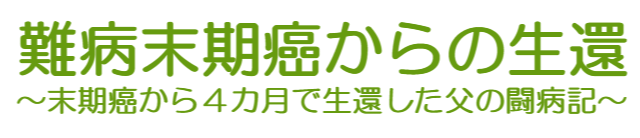ホリスティック医学とは、1960年代、欧米諸国において現代西洋医学の弱点を補うために、西洋医学一辺倒であった医療体系の中に、東洋医学などの伝統医学や各種の民間療法を取り込んで、全人的、全包括的に診療していこうとする医学です。元々、西洋の近代科学至上主義に対する抵抗感からアンチ近代科学、アンチ西洋医学的な発想から生まれているため、一種の「近代文明の否定」から始まったといえるかもしれません。
したがって、化学的に合成された薬やハイテク技術を駆使した検査や手術などに対する強い反発や拒否感があり、そのような薬や技術を用いずに自然治癒力を高めることによって、病気を治せないかと考えます。
Holistic(ホリスティック)という英語は、ギリシャ語のHolos(全体)を語源とした言葉で、全体的とか包括的、まるごとにという意味を持ちます。ヘルス、つまり健康という言葉とも深い関係があります。大変意味合いが深く、広いために、ぴったりとあった日本語訳がなく、そのままカタカナ読みで使われています。また、最近では、ホリスティックという言葉は医学だけではなくて、ホリスティック教育とか、ホリスティックなネットワークというように、医学以外のさまざまな分野でも使われ始めています。
ホリスティックな観点からみた人間とは、身体だけではなく、心や周りの環境、これは自然環境と同時に人間関係や社会環境も含めた環境ですが、これらが有機的につながりあったものである、つまり、つながりの中に存在するものであると考えます。要するに、身体だけが、あるいは心だけが、また、環境だけが単独で健康であるとか病気であるということはありえないのです。
したがって、ホリスティックな健康というのは、ただ単に心身が病気ではないということではなくて、身体と心と環境のバランスがうまくとれている状態のことで、病気とは、そのバランスが崩れている状態と考えます。ですから、病気が治るということは、崩れたバランスが回復して、本来の自分の「全体性」を取り戻すということに他なりません。
身体、心、環境(「場」と言い換えることもできます)が、それぞれ切り離されることなく、ある調和的なバランスを保っている状態であることが、ホリスティックな観点からいう「健康」な状態です。その意味では、部分的に多少の問題があったとしても、全体としてバランスが保たれている間は「健康」といえるのです。
ホリスティック医学とは、このホリスティックな健康観や医学観に根差した医学のことですが、特定の一つの医学をさすわけではありません。ホリスティックな観点に立って、本来人間が持っている自然治癒力を重視、バイオエシックス、ニューサイエンスの考え方などを土台とした全人的な統合医療のことをいいます。
つまり、西洋医学の良さに、気功や鍼などの東洋医学、心理療法、様々な民間療法の利点を取り入れた統合的かつ全人的医療の実現が、ホリスティック医学のめざすものです。さらに予防医学、生命倫理の諸問題までグローバルに見つめる”古くて新しい医学”といえます。
西洋医学では、まず病態を分析して病名を診断し、病名にあった治療法を選択します。しかし、中国医学などの東洋医学では、病態から体内のバランスの異常を判断し、自然治癒力を高めて人間全体のゆがみを是正することが基本になっています。この東西医学の病気に対する見方、考え方の違いを知ったうえで、実際の臨床の現場で取捨選択し、いかにバランスよく統合していくのかが大きな課題です。
たとえば”胃が痛い”といった場合、「人体の中にある胃が病んでいる」というとらえ方が現代西洋医学で、「その人の全体的なバランスのゆがみが胃の病いとして現れている」ととらえるのが、ホリスティック医学なのです。
しかし、この言葉はまだ新しく、意味を知らなかったり、正統医学ではないというだけで偏見を持つ医者もまだたくさんいるという厳しい現実があります。
なぜなら、ホリスティック医学には、西洋医学以外の療法でも、その患者に適する療法であれば、積極的に取り入れるという患者主体の視点があるからなのです。それは、ヨガであったり、気功であったり、アートーセラピー(芸術療法)であったり、いわゆる補完・代替療法のことなのですが、これらは、科学的な検証が不十分なため、どんなに効果がみられても医者はなかなか認めようとはしません。確かに、西洋医学だけを学んだ者にとってこの考え方は、非正統的で、耳障りであり、否定的に考える人がいたとしても、しかたがないのかもしれません。
しかし、西洋医学で治らない患者がほかの手段で健康を取り戻すことがないとはいえません。
私は、「医学という学問は科学的な客観性や普遍性を追及すべきだが、人間とは主観的で多様な存在であるため、人間を扱う医療は科学的なだけでは不十分であり、個別性や多様性をも包括しなければならない」という基本的な医療観を持っています。科学性を基本とする現代西洋医学では得られない効果を他の方法で補うことができるのなら、それでもいいのではないでしょうか。
ホリスティック医学に出合って以降、私は東西の医学の違いについて自分なりに検討・吟味を加えてみた結果、それぞれの「モノサシ」の違いがあることに気づきました(下表)。なお、この比較表は石川光男先生(国際基督教大学名誉教授)や帯津良一先生(帯津三敬病院名誉院長)、芳村思風先生(思風庵哲学研究所所長)などの著書や講演から学んだ知識が基になっています。
かなり強引に東西の医学の特徴を比較してみましたが、その発想、考え方、医療観の違いは、当然ながら東洋と西洋の自然観、生命観の違いに帰するものです。
西洋医学には、生きていくためには獲物をいち早く見つけ、捕まえて、殺すという狩猟民族的な発想がベースにあるため、病気に対しても早期に発見して早期に治療する方法が著しく発達しました。したがって、癌や細菌を殺す抗癌剤や抗生物質などが治療の中心となっています。
ここには、自然は人間にとって苛酷な存在であり、克服すべきものであるという自然観があります。
<西洋医学>
*狩猟民族的発想
獲物を早く見つけ、捕まえるか、殺す。早期発見、早期治療の発達、殺す。医療:抗がん剤、抗生物質。自然は過酷であり、克服するもの。
*考え方・とらえ方
心身二元論。分析的、要素還元的、機械論的、演繹的、実験的、論理的、客観的、普遍的、偏差値(平均値)の医学、画一的、一元的価値観
*西洋的生命観
病気は悪、排除すべきもの(病魔に冒される)、生老病死は変更可能なもの(病は予防、克服できるもの・死は敗北)、進歩的、無限的努力、積極的、成長的、幼児的、(未知なるものへの挑戦、仮説、実験)、(なせばなる、なんとかする)、対立的関係性(心身、理性と感性)
*取り扱う対象:
目に見えるか、測定可能なもののみを扱う(数量化可能:定量的)。
*医療観
病気を取り扱う医学。能動的:病気は治すもの、寿命は延ばすもの。症状とは治療で取り除くもの。
*病気の診療とは?
人間を体と心に分け、さらに体を、臓器から遺伝子まで細分化し、さまざまな科学的手法により病気の原因を診断し、病名にしたがい、定められた治療をする。
<東洋医学>
*農耕民族的発想
囲いで動物から畑を守る。バランス、自然治癒力を重視。守る医療:各種養生法、健康法。自然は恵みであり、調和するもの。
*考え方・とらえ方
身心一如、霊肉一元論。非分析的、包括的、全一的、帰納的、思弁的、観念的、体験的、主観的、個人的。個体差(体質、証)の医学。多様性、多元的価値観。
*東洋的死生観
病気は気づき、病気と共存する(病は苦、持病、病も身の内、病は気から)。生老病死は自然の理(ことわり)(病は人生のプロセスのひとつ・死は必然)。諦観、限界内努力、消極的、不変的、長老的(原理先にありき:陰陽五行説、ヴェーダ哲学)(なるようにしかならない)。循環的関係性(陰極れば陽に転ず)
*取り扱う対象:
目に見えない、測定不可能なものも扱う(気の概念、プラーナなど)(数量化不可能:定性的)
*医療観
病人を取り扱う医学。受動的:病気は治るもの、寿命は超えられないもの。症状とは体調が好転するときの反応:体調好転反応。
*病気の診療とは?
病気を体内のバランス異常ととらえ、自然治癒力を高めて人間全体の歪みを是正する為に病態の把握を重要視、患者の病態に応じて対処法を選択する。
一方、東洋医学には、たとえば畑を荒らすイノシシを見つけて、捕まえ、殺してもいいけれども、畑の回りに囲いを作ればイノシシは畑を荒らせなくなるという農耕民族的発想があるため、殺す治療よりも守る医療としてのさまざまな養生法が発達しました。「養生」は自然治癒力やバランスを重視しています。そして、自然は恵みであり、人間と調和できるものという自然観が基本にあります(とくに東アジア地域において)。
西洋医学は心身二元論に根ざし、分析的、要素還元的であり機械論的な思考をするのに対して、東洋医学では身心一如あるいは霊肉一元論に基づき、包括的、全一的であり観念論的な思弁をします。また、取り扱う対象が、西洋医学では数量化が可能な、目に見える測定できるものに限られるのに対して、東洋医学では「気」など数量化ができない、目に見えない測定できないものも扱うという大きな違いがあります。
西洋医学では、病気は悪で、排除すべき忌むべきもの、医療者にとって死は敗北であり、生・老・病・死は治療によって変更可能なものと考え”なせばなる・なんとかする”といった進歩的で前向きな、可能性に挑戦する姿勢があります。東洋医学では、病気とは必ずしも悪でなく、時には気づきを与えてくれるもので、持病という言葉があるように病気と共存することも重要であり、生・老・病・死は自然の理で、病は人生の大切なプロセスのひとつと考えます。その死生観には”なるようにしかならない”といった諦観があり、ある意味で消極的、後ろ向きな傾向があります。西洋医学は、心・身とか理性と感性というように対立的な関係性で、東洋医学は、陰陽の太極図にみられるように”陰極まれば陽に転ず、陽極まれば陰に転ず”といった循環的な関係性で事物を捉えます。
その医療観においては、西洋医学が客観的に診断した病気を対象としてその症状を治し、寿命を延ばすことが治療の最大の目的であるのに比べて、東洋医学では病人を対象として自然治癒力によって体調が好転し治っていくのを手助けすることが目的であり、寿命は超えられないものと考えます。この、症状とは治療で取り除くべきものなのか、あるいは体調が好転する時の身体の反応なのか、という正反対の見解こそ東西医学の治病観の典型的な違いを示しています。
そして、西洋医学における病気の診療とは、人間をまず身体と心に分け、身体を臓器から遺伝子さらには分子にまで細分化し、精度の高いさまざまな科学的な手法を用いて病気の原因を診断した上で、その病名にしたがい、定められた治療をすることです。一方、東洋医学では病気を体内のバランスの異常と捉え、自然治癒力を高めて人間全体のゆがみを是正することが病気の診療であり、病態の把握を重要視し、患者ごとにその病態に応じた対処法(治療法)を選択します。
現代の医療が、病気は悪で、死は敗北だとする西洋医学の「モノサシ」だけで計られている現在、西洋医学的には治癒不能の末期癌の患者さんのように、その「モノサシ」からはみだしてしまった人たちには東洋医学のような異なった「モノサシ」が必要となるでしょうし、元来東洋的な医療観、治病観、死生観を持った患者さんには、西洋医学の「モノサシ」よりも東洋医学の「モノサシ」の方がしっくりくるのは当然のことかもしれません。
このように、やや私の独断と偏見が入ってはいますが、東西医学を二つの「モノサシ」に分けて比較してみると、西洋医学だけではとてもすべてに対応できないことがわかります。
代替医療とは現代西洋医学以外の医療のことであり、その範囲は極めて広い。これには伝統的東洋医学をはじめ、自然療法、栄養療法、ハー プ療法、マッサージ、気功、瞑想、祈りまで様々なものがある。これらに共通することは、 全体性や自己治癒力の存在を重視したアプローチがなされているという点である。
ホリスティック医学では、全体性や自己治癒力といったことを重視する。 そのような視点を持つた治療法は西洋医学にはなく、自ずと代替医療に目が向けられるようになってきたのも当然の結果である。
なお代替医療という言葉は主にアメリカで使用されており、イギリスでは補完医療(complementary medicine)という名称が使われている。90年代に入ってからは、この両者を結びっけた補完代替医療 (Complementary and Alternative medicine;CAM)という名称が欧米各国で使われるようになってきた。
なお以下表に、日本で比較的利用されている代替医療の臨床分類を示した。
1) 医療体系化がなされているもの
中国医学、アーユルヴェーダ、ホメオパシー、ナチュロパシー(自然療法)
2) 主にセルフコントロール法として利用されているもの
自律訓練法、 リラクセーション法、バイオフィードパック療法、瞑想、ヨガ、気功
3)静的な他者療法
鍼灸、按摩、マッサージ、指圧、アロマテラピー、リフレクソロジー、セラピューティック・タッチ、レイキ、催眠療法、磁気療法
4)動的な他者療法
整体、操体法、臨床動作法、カイロプラクティック、アレクサンダー・テクニック
5)芸術や環境、動物などを利用したもの
カラーセラピー、音楽療法、絵画療法、芸術療法、温泉療法、園芸療法、タラソセラビー、アニマルセラピー
6)生物学的療法
健康補助食品(サプリメント)、ハープ療法、ビタミン療法、漢方薬、マクロビオティック、絶食療法、フラワーレメディ
7)主にがん患者を対象とした代替医療
健康補助食品(プロポリス、アガリクス、AHCC、サメの軟骨など)、丸山ワクチン、蓮見ワクチン、生きがい療法、サイモントン療法
現在アメリカ国民の4割以上が代替医療を利用しており(2003年現在)、すでに現代社会においては必要不可欠な存在となっている感がある(Eisenberg D.M.et al., 1998)。
その動きと呼応するように、西洋医学の分野においても代替医療の有用性を認め、それらを積極的に取り入れていこうとする動きが出てきている。
すなわち西洋医学は感染症や救急疾患に対しては、かなりの有効性が認められているが、慢性疾患に対しては非力だと言われている。
逆に代替医療は慢性疾患や予防医学には大いにその効力を発揮する。
このように、両者とも対象疾患に対する得手不得手が存在する。
そこでお互いの長所を取り入れ, 患者に対してより有効な治療を提供しようとするアプローチが統合医療である (帯津, 1998)。
これは主に西洋医学を実践する医師たちが中心となって行っている新たなる医療の動きである。
統合医療では、西洋医学的治療法と代替医療を積極的に利用していくことはもちろんのこと、全体性や自己治癒力の重視、患者主体の医療といった側面も持ち合わせている。
これはまさにホリスティック医学そのものであると言ってもよいほどである。しかし実際には、ホリスティック医学という言葉はここではあまり使われない。
それは初期のホリスティック医学には反西洋医学的イメー ジがあり、今なおアンチ西洋医学の立場から極端な代替医療を行っている実践家が数多く存在していることも影響していると思われる。
しかしこの点を除いても、統合医療とホリスティック医学とでは多少異なる部分が存在している。
それはスピリチュアルな側面に関してである。
ホリスティック医学の場合、人をマインド・ボディ・スピリットの有機的統合体としてとらえ、その視点から様々なアプローチがなされている。
しかしこのスピリチュアルな側面は、宗教的要素や非科学的な印象が強いため、西洋医学を実踐する医療者たちにとっては多少の抵抗感のある部分でもある。
そのため統合医療では、まだマインド・ボディの世界にとどまっている傾向が強い。
今後、統合医療がさらなる発展をしていく過程において、代替医療が西洋医学に積極的に取り入れられるようになったのと同様に、スピリチュアルな視点やアプローチも大いに取り入れられるようになる日もそう遠くはないと思われる。実際、夕一ミナルケアの分野においては、すでにスピリチュアルな視点を抜きにしては、それを語ることはできなくなっている。
そうなった時に初めて、以前のような西洋医学に対するアンチテーゼとしてのホリスティック医学ではなく、マインド・ボディ・スピリットの概念を基本に据えた真の意味でのホリスティック医学が生まれることになる。
日本国内で代替医療・統合医療・伝統医学などを取り入れていると思われるクリニック一覧です。ネットで調べた情報ですのでこれがすべてのクリニックではないですし、掲載した治療内容が正しいかどうかはご自身でよく調べて下さい。我が家では利用したことが御座いませんので、如何なる場合も責任は負えません。
尚、これらのクリニックや病医院で私の父の末期癌を完治に導いた米国UCLA研究の免疫賦活物質(最新版の医療機関向け免疫賦活物質BRM)を扱っているかどうかは私では分かりません。
| 都道府県 | 医療機関名 | 診療・治療内容 |
| 北海道 | 響きの杜クリニック | 婦人科・産科・点滴療法・ホメオパシー・温熱療法・アロマテラピー・プラセンタ療法・デトックス・アンチエイジング 他 |
| 北海道 | 癒しの森内科・消化器内科クリニック | 消化器科・内科・腫瘍内科(がん統合治療) |
| 岩手 | さやかクリニック | 内科・心療内科・女性内科・産婦人科・漢方内科・アレルギー科 |
| 宮城 | 市川内科電力ビルクリニック | 内科・消化器科・漢方科 |
| 秋田 | あきたすてらクリニック | 点滴療法・サプリメント外来・形成外科・皮膚科 |
| 山形 | 十日町ようこクリニック | 内科・女性内科・サプリメント療法・点滴療法 |
| 栃木 | 半田醫院 | 一般内科・消化器内科・栄養治療・統合医療 |
| 栃木 | 谷口医院 | 内科・小児科・産婦人科・皮膚科・漢方外来・統合医療・点滴外来・抗加齢治療・プラセンタ治療 |
| 群馬 | 佐藤医院 | 産科・婦人科・予防医療(栄養療法・サプリメント療法他) |
| 岐阜 | 船戸クリニック | 内科・胃腸科・整形外科・泌尿器科・心療内科・循環器科・麻酔科・リハビリ科・婦人科・アトピー・更年期外来・がん治療・温熱治療・点滴療法・漢方・電子治療・サプリメント 他 |
| 埼玉 | あいオリエンタルクリニック | オーソモレキュラー療法・サプリメント療法・漢方療法・自律神経調整療法 |
| 埼玉 | 帯津三敬病院 | 内科・呼吸器内科・循環器内科・糖尿病内科・神経内科・心療内科・漢方外来・外科・消化器外科・乳腺外科・整形外科・脳神経外科・泌尿器科・リハビリテーション科・緩和ケア・代替療法 |
| 千葉 | 協和医院 | 内科・心療内科・循環器科・婦人科・女性専門外来・生活習慣病外来・更年期外来・認知症外来・代替医療・オーソモレキュラー |
| 千葉 | すぎおかクリニック | 内科・循環器科・心臓内科・糖尿病内科・サプリメント療法・点滴療法・キレーション療法 |
| 東京 | 赤坂溜池クリニック | 心療内科・精神科・ホリスティック医学・統合医療 |
| 東京 | イーハトーヴクリニック | がん外来・温熱療法・催眠療法・ヒーリング・アロマトリートメント・アーユルヴェーダ 他 |
| 東京 | 帯津三敬塾クリニック | 漢方・ホメオパシー・サプリメント・漢方ドック |
| 東京 | 銀座東京クリニック | がん治療・漢方・補完・代替医療・サプリメント・点滴療法・プラセンタ療法・水素療法・アンチエイジング療法 他 |
| 東京 | 健康増進クリニック | がん外来・漢方・鍼・アトピー・アンチエイジング・心理療法・点滴療法・キレーション療法・ホルミシス療法・オゾン療法・プラセンタ療法・サプリメント療法・食事療法 他 |
| 東京 | タカラクリニック | がん治療専門・TCTP療法・補完医療・代替医療 |
| 東京 | 鶴見クリニック | 免疫強化と原因を改善する治療・ファスティング・温熱治療・サプリメント・ホルミシスライフスタイル改善指導・食養生法・デトックス療法 他 |
| 東京 | 東洋医学研究所付属クリニック | 内科・整形外科・リハビリテーション科・放射線科・自然医療 |
| 東京 | ナチュラルアートクリニック | 内科・麻酔科・ペインクリニック・統合医療・栄養療法・ナチュラル療法 |
| 神奈川 | ふるたクリニック | がん治療・点滴注射療法・サプリメント |
| 神奈川 | 柳川クリニック | 消化器科・胃腸内科・循環器内科・呼吸器内科・内科・心療内科・内視鏡検査・点滴療法・サプリメント外来・東洋医学科・プラセンタ療法 他 |
| 愛知 | 広瀬クリニック | 内科・小児科・皮膚科・漢方・サプリメント・プラセンタ・点滴療法・放射線ホルミシス |
| 愛知 | 恒川クリニック | 内科・消化器科・皮膚科・漢方・サプリメント外来・温熱療法・統合医療・食事指導・養生指導 他 |
| 滋賀 | 彦根市立病院 | 総合内科・外科・消化器科・循環器科・呼吸器科・小児科・婦人科・皮膚科・麻酔科・緩和ケア科・リハビリ科・栄養科・がん相談他・西洋医学・温熱療法・ヒーリング・ホメオパシー・サプリメント・点滴療法 他 |
| 奈良 | 慈恵クリニック | 内科・外科・胃腸科・リハビリ科・肛門科・がん相談・免疫療法・プラセンタ治療・栄養療法 他 |
| 石川 | 新クリニック | 一般内科・肝臓外来・禁煙外来・漢方治療・栄養療法・内視鏡検査・点滴療法 |
| 京都 | 明治国際医療大学付属統合医療センター | 内科・漢方内科・心療内科・睡眠外来・禁煙外来・はりきゅう治療・アロマセラピー・鍼灸治療 |
| 大阪 | IGTクリニック | 血管内治療・温熱治療・免疫治療・高濃度ビタミンC療法・がん検診 |
| 大阪 | みうらクリニック | 一般内科・生活習慣病・がんなどの難病・アトピー・東洋医学・漢方・栄養療法・断食療法・自律神経免疫療法・点滴療法・ホルミシス療法・心理療法・手技療法・エネルギーヒーリング 他 |
| 大阪 | ラ・ヴィータメディカルクリニック | 一般内科・外科・循環器内科・統合医療・点滴療法・キレーション療法・プラセンタ療法・サプリメント・ホメオパシー・ヒーリング・東洋医学・デトックス療法・手技療法 他 |
| 兵庫 | ナチュラル心療内科クリニック | 心療内科・がんの心理療法・分子栄養療法・アロマセラピー 他 |
| 兵庫 | SINGA宝塚クリニック | がん治療・温熱療法・高濃度ビタミンC点滴療法・分子整合栄養学療法・免疫療法・電子治療 |
| 島根 | 真理渡部歯科クリニック | 一般歯科・口腔外科・矯正歯科・予防歯科・審美歯科・統合医療・オーソモレキュラー療法・点滴療法・キレーション療法 |
| 岡山 | すばるクリニック | 心療内科・精神科・腫瘍内科・アレルギー科・漢方・温熱療法・気功・呼吸法 他 |
| 香川 | 桑島内科医院 | 内科・胃腸科・皮膚科・小児科・漢方・栄養療法・点滴療法・温熱療法 |
| 愛媛 | きい麻酔科クリニック | ペインクリニック・点滴療法・キレーション療法・オーソモレキュラー療法・がん治療・電気治療 |
| 福岡 | 葉子クリニック | 西洋医学・東洋医学・食事療法・ホメオパシー・自律神経免疫療法・温熱療法・高濃度ビタミンC点滴療法・ホルミシス療法・こころのケア 他 |
| 佐賀 | Y.H.C.矢山クリニック | 内科・外科・小児科・アレルギー科・リウマチ科・歯科・がん治療・ホメオパシー・デトックス療法・フラワーエッセンス・アンチエイジングドック 他 |
| 熊本 | 松田医院 | 内科・小児科・麻酔科・心療内科・アレルギー科・漢方内科・サプリメント・栄養療法・鍼灸・気功エネルギー療法・点滴療法・温熱療法・自律神経免疫療法・音響療法・キレーション療法 他 |
| 鹿児島 | さくらクリニック | 一般内科・がん外来・更年期障害・パーキンソン病・アトピー外来・ニキビ治療・健康美容外来・点滴療法・プラセンタ療法・オゾン療法 他 |
| 沖縄 | ハートフルクリニック | がんの統合医療・サプリメント外来・点滴療法・代謝栄養療法・プラセンタ療法・キレーション外来・血液療法・アンチエイジングドック 他 |